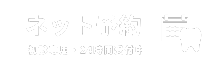皆さんこんにちは、サブチーフ衛生士の大澤です❣️まだまだ残暑が厳しいですね。。。
夏の疲れが出始める頃ですので、しっかり栄養や睡眠、休息を取ってお身体お大事に元気にお過ごしくださいませ😃✨
さて、前回の石垣チーフのブログで、虫歯になる原因や、虫歯がどのように進行するのかがお分かりになったかと思います。
今回は「虫歯になったのになぜ痛くならなかったの??」の謎を解説させていただきます🎓
まず、前回の進み具合とは別に、虫歯には2種類に別けられます!
初めてできる虫歯が【一次ムシ歯】、一度治療を受けた虫歯を【二次ムシ歯】といいます。
●1次虫歯●
噛み合わせの溝や、歯と歯の間から進行する「1次虫歯」は、歯の表層のエナメル質から発生します。
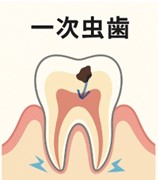
それが、エナメル質の下で神経を守る役割をしている象牙質に到達するとお痛みやシミという症状が出ます。
歯の色が白く抜けたり、柔らかく変質して穴が空いたりと目視しやすい為、症状が出る前にご自身で気がついたり、メインテナンス時に比較的初期の段階で発見されやすいのが特徴です。

また、虫歯の進行がまっすぐ神経に向かって急性的に進むため痛みが出やすいのです。
- 2次虫歯●
それに対して、詰め物や銀歯などで修復して治療が完了した歯が再度虫歯になる事を「2次虫歯」と呼んでいます。

なぜ再び虫歯が発生してしまうのか??など2次虫歯についての詳しいお話しはまた別でお伝えしますね!!
さて、本題にお話しを戻します。
修復した部分の隙間から再度虫歯になってしまった場合、詰め物が外れたり、自覚症状が出るまでは見つかりにくく、症状が出てしまうと神経処置をしないといけないくらい深刻な虫歯になっている事が多いのです。
なぜそこまで進行している虫歯なのに痛みのサインが出ないのでしょうか??
それは歯の治療による刺激によって、「2次象牙質」という歯の神経を守るための組織が発生するからです!
ゾウさんじゃないですよ!
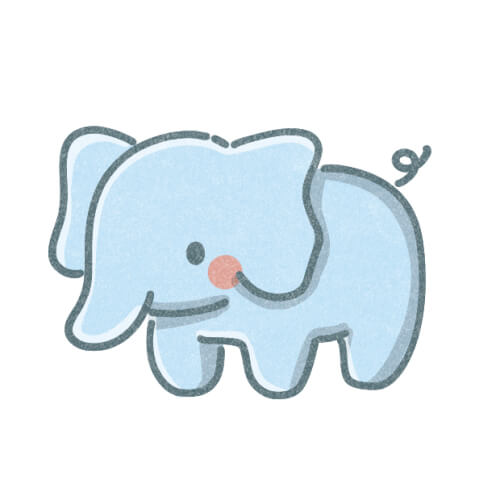
生体防御反応により、神経を守るために作り出される2次的な組織です。
★2次象牙質のはたらき★
- 2次象牙質が作られると、ムシ歯と神経までの距離が遠く長くなるため、痛みを感じにくくなる
- 神経の部屋も少し狭くなるため、刺激を感じにくくなる
2次象牙質のこのような働きにより、神経が守られるため痛みがなく虫歯が進行していきます。
また、2次ムシ歯の進行がジワジワとゆっくり広がる慢性的なもののため、痛みの感受性が鈍くなることも痛みを感じにくい理由の一つです。
2次象牙質の発達により神経を守れるメリットはありますが、痛みに鈍くなる事で自覚症状が出にくくなります。
更には詰め物の下で起きる事なので、レントゲン写真や精密な検査でないとムシ歯が見つかりにくいというデメリットもあります。
いずれにせよ、定期的なメインテナンスや日々の歯ブラシにより細菌感染のリスクを減らしたり、
詰め物などのチェックの為にもお口の中を管理することはとても大切なことです。
年に1度のレントゲン撮影にもぜひご協力いただき、早期発見できますよう尽力しますのでご理解のほど、宜しくお願いいたします。
次回は、神経を保護するためのお薬について亀村さんにバトンタッチ致します!